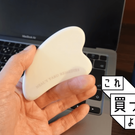アメリカの学校の教室では、このような光景がよく見られます。
「地球の大気中にもっとも多く含まれる成分は何ですか?」と先生が質問すると、生徒は手をあげて答えます。
「酸素?」
「ちがいます」
「炭素?」
「ちがいます」
「水素?」
「ちがいます」
「窒素?」
「そうです!」
そして、先生はおもむろに窒素の特性について説明をしはじめます。
しかし、このような正解を見つける競争の中で、学習に重要な機会を損してしまっています。カリフォルニア州立大学バークレー校の「Greater Good Science Center」のAmy L. Evaは、「本当に何かを学んだり生徒が学ぶのを助けるには、失敗に注目したほうがいい」という説得力のある説を述べています。複数の研究で、答えが間違っていても不安にならなければ、正解したあとにそれだけ正解を記憶しやすいことがわかったのです。学習の過程全体が、「正解か」「不正解か」という不安に支配されず、生産的で満足感のあるものになります。
しかし、アメリカ人は間違えることに非常に強い嫌悪感を持っているように思えます。心理学者のHarold StevensonとJames Stiglerの有名な研究では、アジア人とアメリカ人の生徒に違いが見られました。Carol TavrisとElliot Aronsonの『Mistakes Were Made (But Not By Me)』という著書の中で、その発見は以下のように書かれています。
小学校5年生まで、日本の小学校で最低の成績が、アメリカの小学校では最高の成績よりも勝っていました。その理由を探るべく、StevensonとStiglerは、アメリカと中国と日本の小学校の授業を比較するのに10年を費やしました。そして、日本の少年が黒板に立方体の絵を描くのに四苦八苦しているのを見て、彼らはひらめきました。StevensonとStiglerが、不安やいたたまれない気持ちを募らせていったのに、少年は失敗を繰り返しながら、45分間そのことに奮闘し続けたのです。しかし、少年自身はまったく意にも介していませんでした。アメリカ人の研究者である彼らは、本人以上に嫌な気分になったのはなぜか疑問に感じました。「アメリカの文化では、失敗することに対して心理的に大きな代償が必要ですが、日本ではそこまで必要ではないようです。日本では、失敗やミスや間違いは、すべて学習する過程で自然に起こることだと思われています。(少年は最終的に立方体が描けるようになり、クラスメイトは歓声を上げました)」。
これは教師がどのように反応するかに、大いに関係があるかもしれません。Evaは、同じ研究について書いており、アメリカの教師は失敗は基本的に無視して、正解を答えた生徒をほめると指摘しています(おそらく、アメリカ人ならこれまでのすべての授業で思い当たるふしがありそうです)。
しかし日本では、先生が生徒をほめることはほとんどありません。それよりも、「正解と不正解どちらの答えにも、そこにたどり着いた様々な道筋」を検証します。正しい答えに賞賛もなければ、間違った答えに(ブブーと)ブザーが鳴ることもありません。すべてが学習という、大きく長く複雑な道のりの一部にすぎないのです。
親や教師が、子どもが実際に学ぶ前に材料について予測させることは、子どもが間違った答えについて考えるのを助ける方法の1つです。Scientific Americanには、教科書で勉強する時に役立つアイデアとして、その章を読む前に章の最後の質問に答えてみると書いてあります。もしくは、「パブロフの条件付け」という見出しがあったとしたら、「パブロフの条件付けとは何でしょう?」という風に、見出しを質問に変換します。生徒はおそらく間違えるでしょう。
しかし、教科書を読みはじめ、学習する材料に触れる時には、最初の質問によって子どもの脳は学ぶための準備ができています(試してみたい人は、何か知りたいことが出てきたら、ググる前に答えを予測してみてください)。
親にとっては、失敗に対して健全な反応を示すことも大事です。Evaの娘が幼児だったころ、食事中に目の前で娘がよく牛乳をこぼしており、「おっと、しょうがない、大したことじゃないよ、さあきれいにしようね」と言っていました。失敗は人生の一部だと、親が子どもに教えるのが早ければそれだけ、すばらしい答えにたどり着かなければならないと考える心に、もっと余裕ができるはずです。
Image: Monkey Business Images/Shutterstock.com
Source: Annual Review, The New York Times, Amazon, Scientific American
Michelle Woo - Lifehacker US[原文]